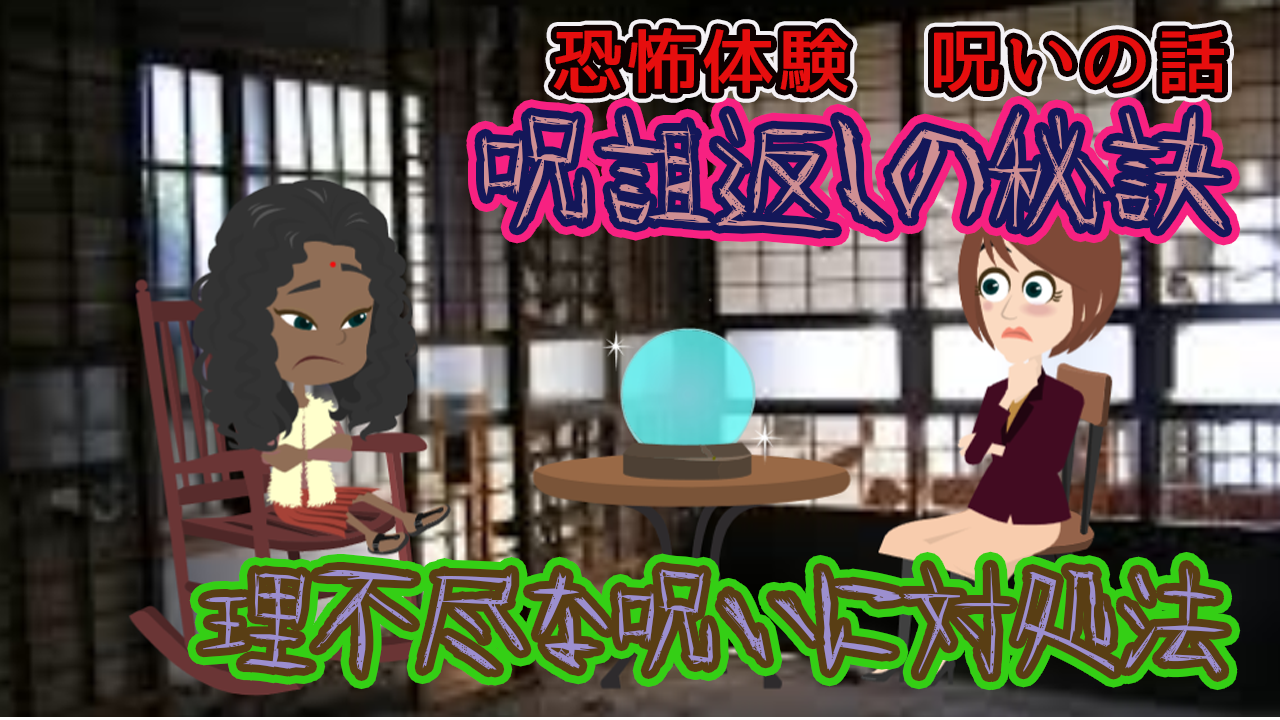![]()
クチナシの壺

[su_youtube url=”https://youtu.be/3q6p6I_wP-s”]
「壷ってさ、誰がどう見ても壷だよな」
「は?」
陶芸教室の開始前に、幼なじみの中央は話を振ってきた。 「ちゅうおう」と書いて「なかお」と読む。なんとも面白い名前である。 俺と中央は師匠の亀山先生に頼まれて、倉庫から作業道具を探している最中だ。中はゴミや虫だらけで気色悪く、何度も道具を出し入れしているはずなのにすぐに蜘蛛の巣が張られる。
「漢字の話だよ。こんな偶然あるか?」
「いや、象形文字ってやつだろ」 確か、物の形をかたどって書かれた文字の事だ。壷が象形文字なのかは分からないけど。 中央の言いたい事は、どうやら壷という漢字が壷そのものに見えるという事だろう。
「あと、串な。あれも誰がどう見たって串だ」 何を言ってるんだと苦笑する。 俺は中央の馬鹿だけど実直なところが好きだ。幼稚園から大学までずっと一緒の、幼なじみであり腐れ縁でもある。この先、何があっても一人にはしないだろう。
昔から何をするにも一緒だった。 中央がサッカーを始めたら俺も一緒に付き合って、俺がカードゲームを始めたら中央も一緒に付き合って。お互いの事について知らない事は何一つない。 この陶芸教室も中央からの誘いで参加したくらいだ。
「……なんだ、これ?」 中央の素っ頓狂な声がする方向に目を向けると、ブルーシートの隙間から升のようなものが顔を覗かせる。興味本位で捲ってみるとそれは真四角の壷であった。
「亀山先生の失敗作か?」 確かに、凡人の俺達から見ると形が歪んでいる気はするけれど、それがいわゆる「味」なのかもしれない。それに、亀山先生の性格を考えると失敗作ならすぐに壊すだろう。 そもそも、失敗作なんてものを今の今まで一つも見たことがない。
霞の天才。世間が亀山先生を語る際に評する肩書きだ。 若い頃から陶芸の道に進んだ訳ではなく、かといって大人になってから技術を極めた訳でもない。突然、昔からそうであったかのように亀山先生の陶磁器は歴史に根付いていた。 当たり前にそこにあって、いつからかそこに佇んでいた存在。 悪口や悪評といったマイナスイメージを一度も聞いたことがなかった。
「この壷さぁ、売ったら高いのかな?」
「そりゃ高いだろ。先生にとって駄作でも、世間から見れば大作なんだろうからな」 そうだよな。と、誰に話しかけるでもなく中央が呟く。 いつもの馬鹿みたいに明るい中央にしては、珍しくどこか歯切れが悪かった。
「中央、お前、売るなよ?」
「売るわけねーだろ」 いくら中央でもそんな事する訳ないかと苦笑する。 あいつは馬鹿だけど根は真面目な良い奴だ。冗談で叩いた軽口だとしても申し訳なく思う。
「それより早く教室に戻ろうぜ、中央」 その時、ガシャンと鈍い音がした。
「……どうした?」 振り向くと、中央が青ざめた表情で床を凝視していた。 先ほどまでは艶美な光沢を放っていた壷が、今や無惨にも粉々になっていた。
「お前、これ割ったのか?」
「違う。壺が、勝手に、滑って……」
「そんなわけあるか」 とにかく、まずは破片を片付けなければいけない。 掃除用具も倉庫にあるだろうと探していると、辺りがシィン、と静まり返る。
「……おーい」 確認すると友人の姿が何処にもなかった。
「あいつ、まさか逃げたのか?」 代わりに、白くて大きな六つの花弁がぽつんと置いてある。
「なんだこれ」 壷の破片を拾い上げると、これは……クチナシの花だ。 なんでこんなところに……。 それより、あいつは何処に行ったのだろうか。 陶芸教室は見通しの良い場所にある。こんな短期間で見失う事はないはずだ。
―あれ、あいつの名前ってなんだっけ?
「どうしたんだい?」 ハッとして我に返る。声のした方を振り向くと、いつの間にか亀山先生が立っていた。
「いや、あいつが、その……」 割れた壺の欠片とクチナシの花をしばらく眺めた後、あぁ。と、小さく頷く。
「クチナシの壷を落としてしまったんだね」
「クチナシの壺?」 名前があるという事は失敗作ではないのだろうか。だとしたら、どうして。
「あの、急にあいつがいなくなって、あいつって言うのは、えぇと……」
「あの子の名前は、実に不運だった」
「どういう事ですか?」 それに、亀山先生はまだあいつの名前を覚えているのか。
「なぁに、ただの言葉遊びだよ」
「言葉遊び?」
「ただ、この壷はそんな言葉遊びを現実にしてしまうんだ」
『だから、一人になってしまったんだよ』 誰に話しかけるでもなく、亀山先生が呟いた。
しばらく呆然とする。亀山先生の言わんとしている事が分からなくて頭が混乱した。
「この壷には『呪い』が詰まっていてね」
「呪い、ですか?」 失礼な話だけど、亀山先生もぼけ始めてきたのかと勘ぐってしまう。
「君はこの壷に触れたかい?」
「……破片だけですけど」 亀山先生が「ふぅん」と俺を眺める。
「いずれ君にも『呪い』が降り掛かるだろう」
「あの……」
「今日はもう帰りなさい。ここは私が片付けておこう」 いつもの厳格な表情はどこにもなく、ねばついた歯を見せながらにたにたと笑っていた。
ご飯を食べていても、お風呂に入っている間も友人の名前が思い出せなかった。 奇妙な事にあいつと一緒に撮った写真にも、動画にも、卒業アルバムにもあいつの名前が載っていないのだ。大学の教授も知らぬ存ぜぬで、あいつの両親に電話しても不審がられるばかりだった。ウチに息子なんていません、と。 友人の失踪、名前の消失、クチナシの壺。そして、呪い。
訳のわからない事が続き、大学にも陶芸教室にも顔を出さなくなって二週間あまりが経つ。 最近はあいつの生きた痕跡を探そうと、思い出の地を巡る日々だ。 ゲームセンター、漫画喫茶、バッティング場。あいつの名前や失踪の原因がどこかに隠されていないか神経を注ぐ。どこか、どこか、どこか、どこかに。 『いずれ君にも『呪い』が降り掛かるだろう』 亀山先生の言葉を思い出しては心の底から身震いがする。 俺もあいつと同じように存在自体が消えてしまうのだろうか。
「……あ」 ふと、行き着いた先は陶芸教室だった。 二週間も顔を出していないので気まずくもあり、不安もあって踵を返そうとする。 けれど、 あいつの事にせよ、自分に降り掛かろうとする呪いにせよ、いずれ来ないとならないのだ。 覚悟を決めて陶芸教室の門をくぐる。それと同時に十七時の鐘が鳴った。 ギシ、ギシと軋む床を進むと、教室に亀山先生の後ろ姿を捉える。 いつもはジャージ姿なのに、今日は珍しく絵羽模様の和服を纏っていた。 「亀山先生」 部屋に入ると、まだ夕方だというのに暗闇に包まれていた。 ろくろを回すのに集中しているのか、俺の方を振り向かずにしばしの時間が流れる。 この時の亀山先生の邪魔をしてはいけない。 そう思いつつ、深淵に佇むその背中に声をかけずにはいられなかった。 「あの……」 ろくろを回す手が止まると同時に、時間も止まったかのような錯覚に陥る。
亀山先生が振り向くと能面のような無表情で迎えた。
「その、今まで無断欠席してすみませんでした。月謝は――」
「払わなくていいさ。私は亀山じゃないからね」 厳格さと静謐さを伴った声だった。
「……何の冗談ですか?」
「冗談ではないよ。私は日本呪術研究呪鬼会の呪術師です」
「呪鬼会?」
聞いた事のない名前に戸惑っていると、手振りだけで椅子に座るよう促される。 おずおずとしながらも老人から目を離さずに座った。
「代わりに呪いをかけてくれる、って事ですか?」 こんな不気味な所に長居したくないのに、なぜだか興味を惹いてしまう。
「それは呪いの内容にもよるね」
呪術師と名乗る老人が人差し指、中指、薬指の三本を立てる。
「一つ、依頼者の代わりに我々が呪いを実行する。二つ、依頼者が呪いの概念を体現する。三つ、呪いを物に肩代わりさせる。一口に代行と言ってもその性質は様々なんだ」 ある一つの道を究めると、おかしな事を言い出すのだなと戸惑う。いや、本人の頭の中にはちゃんとした道筋があるのだろう。俺達のような凡人にはその過程が理解できないだけだ。 と、思い込む。 思い込まないと、恐怖に飲み込まれそうになるのだ。
この、亀山先生のガワだけを被った『何か』の恐怖に。
「君は呪いに対してどんなイメージがあるかな」
「……呪い」 言われて、しばらく逡巡する。
「まぁ、代表的なもので言えば藁人形ですよね」
「『呪いを物に肩代わりさせる』方法。もっとも一般的で、もっとも効果のある『呪い』だ」
ふと、クチナシの壺を思い出す。あれには呪いが詰まっていると亀山先生、あの人すらも本物かどうかは今となっては分からないけど、つまり壺に呪いを代行させたという事なのか。
「さて、本題に入ろう。君はどうしてここに訪れたか分かるかな?」
「それは、気付いたらたまたま目の前にいて……」
「そんな事はない。呪術師との対話は明確な理由がないと巡り合わない」
亀山先生が……いや、老人の座る椅子が鈍い音を立てて軋む。
「呪い代行を望んでいる者か、直接誰かに呪いをかけたい者。それと――」 それと、 「君のように、すでに呪われている者か」 「呪われている……」 馬鹿げた話だと一蹴する事はできなかった。現に友人が失踪しているし、その友人の名前も思い出せない。両親ですらそいつの存在を忘れているのだから。
「俺はこれからどうなるんですか?」 老人がしばらく考え込む。という振りをしているだけにも思える。
「おそらく死なない。死なないが、きっと死んだ方が楽なんだろうね」 回りくどい話し方にやや苛立ちを覚える。
「クチナシの壷は『新言語』の『呪い』を代行しているんだよ」
「新言語?」
「要は言霊さ。壷に言葉を封じ込めるとその言葉の持つ概念が失われる」
壺を割った時にクチナシの花が出てきた。封じ込めたのは……クチナシ?
「亀山が壷に何を封じ込めたのかが鍵になるだろう」
「クチナシ、ですか?」 花言葉が何か関係するのだろうか。
「それは副産物だろう。封じた言葉が形になったもの。それがクチナシだと思っていい。問題は何が具現化したか、だ。君は亀山について何か不審に思う事はないかい?」
「不審……そんなの特には――」
いや、あれも不審と言えば不審なのかもしれない。 亀山先生を蔑む感想や評判はほとんど、というより、一つも見当たらないのだ。 雑誌にも、SNSにも、テレビやラジオにも、彼を侮蔑する言葉の一欠片もなかった。 人が人を評価する以上、そこにあるのは優しさや正しさだけで満たされる訳はない。 どれほど有名な存在にも、いや、有名な存在だからこそ一定数のアンチは存在するはずだ。 光が強くなれば強くなるほど、闇が濃くなるように。 老人が俺の心を見透かすように頷く。
「おそらく亀山は誹謗中傷、自分に不利益となる『不評』を封じ込めたのだろう」
「だから……」 だから、マイナスイメージがない。だから、祭り上げるような評価しかない。
「でも『不評』がどうしてクチナシなんかに……」
「簡単な事さ。見えなければ、聞こえなければ、知らなければ、それは無と同じだ」
ニタァ、とねばついた歯が覗く。
「簡単な言葉遊びさ。『死人に口なし』とは、よく言ったものだろう」
呪鬼会の呪術師と名乗る老人曰く、俺に対する『呪い』は数日中に起こるそうだ。 『不評』の概念が詰まったクチナシの壺。中にはどれほどの悪意を溜め込んだのだろう。 欠片とはいえ、その壺に触れた。 憎悪の塊が全て襲い掛かってきたら俺はどうなる? あいつは名前を失って消えた。
じゃあ俺が名前を失うと何が起きる。 …………あれ? 俺の名前って、なんだっけ? 今さらな話だけど、考えればおかしな事ばかりだ。 『不評』の概念を失っただけなら、あいつはどうして失踪したんだ……いや、ここまでになるともう消滅だ。それに、失ったはずの『不評』を俺が覚えていられるのもおかしい。 クチナシの壷に封じ込めたのは、もっと別の『何か』なのか? なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。
「簡単な言葉遊びさ。『死人に口なし』とは、よく言ったものだろう」 老人の言葉が頭の中を這い回る。 クチナシ? なぜだか名前の思い出せない友人が、口を失って一人になった? 一体どういう事だろうと考える。 考えて、考えて、考えて、考えて、考えて、考えて。 ……あ。
そのとき、「中央」一瞬だけ友人の名前を思い出した。 『だから、一人になってしまったんだよ』 そうか。不評を声に出す口を失ってしまったから。 亀山先生はずっと言っていたじゃないか。単純な言葉遊びだって。 単純な、言葉遊びだ。 だとしたら、俺はどうなる?どんな事が起こる? この壺の名前はクチナシの壺だ。 ゾッとする。 あぁ、そうだ。俺の名前は――
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係がありません。